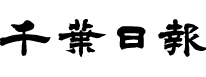2023年9月4日 05:00 | 有料記事

海面から出ているのが関東大震災で隆起した「大正ベンチ」と呼ばれる段丘。右手には元禄地震で隆起した段丘も見える(館山市見物、県立中央博物館提供)

房総半島の成り立ちを説明する八木令子上席研究員=千葉市中央区の県立中央博物館
房総半島は沈み込む3枚のプレートの上にあり、数百万年前から地震による隆起で地形が形作られてきた。専門家らは「千葉は地震と切っても切り離せない地域」と指摘する。関東大震災でも館山市や南房総市など県南部を中心に、1・5メートルほど地盤が隆起。海岸線が変化し、漁港の水深が浅くなり漁船の通行に支障が出るなど漁師町に大きな打撃を与えた。被害は今も各地に残る石碑に刻まれている。
北米プレートの上にある房総半島は、南側からはフィリピン海プレート、東からは太平洋プレートが沈み込み、3枚のプレートが複雑に重なる地域。県立中央博の高橋直樹上席研究員(地質学・岩石学)は「これほど複雑で大きな地震が起きやすい地域は、世界でも他にない」と話す。
関東大震災時は、北米プレ ・・・
【残り 8624文字】